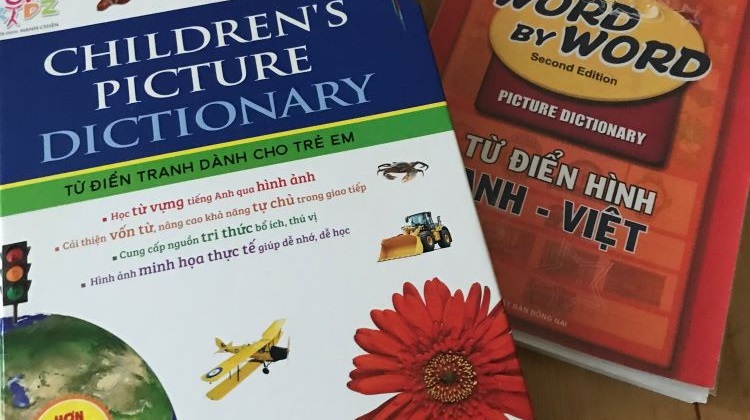翻訳学習
2022.11.11

翻訳語り(2)翻訳家に「向いている」人ってだれ?
「自分は翻訳家に向いているのだろうか……。」そう悶々と考えていた時期がわたしにもありました。翻訳を仕事にしたいけれど、才能があるのかわからないし、まったく見込みのないものの勉強を続けるのは不安、という気持ちを抱いたことがある人は多いのではないだろうか。
「適性」は存在するかもしれないけれど
それが何であれ、何らかの職業に就くことを検討するとき、たいていの人は考えてしまうものだろう。自分はほんとうに料理人に向いているのだろうか、美容師に向いているのだろうか、教師に、会社員に、アイドルに向いているのだろうか……。
どうせ何か仕事をするのなら、できれば自分に向いていて、才能を生かせる職業に就きたいというのは当然の欲求だ。自分の適性がわからないのは心もとないし、もし自分にその職業に必要とされるセンスがないのなら、できれば早いうちにだれか(神様とか、何でもよくわかっているはずのだれか)から、その事実を教えてもらいたいと思う。
わたしもかつてそうだった。これが現代だったなら即、スマホで「翻訳家 向いている人」で検索しているところだが、わたしが学生のころにはスマホどころかネットも普及していなかったので、ただ漠然とささやかな憧れともやもやとした不安を抱いていただけだった。
試しに今、Googleで「翻訳家 向いている人」で検索してみたところ、見つかった条件としてはたとえば以下のようなものがある。
責任感がある
忍耐力がある
知的向上心がある
謙虚である
健康管理ができる
時間を守る
失敗から学ぶことができる
日本語でよい文章を書く力がある
これは翻訳業界の片隅にいるわたしから見てもどれももっともだし、そりゃそうだろうなと納得する。
だけど考えてみてほしい。これらの条件は最後のひとつを除いて、どの仕事でも言えることなのではないだろうか。だからこれは「翻訳者に向いている人」というより、「仕事をするのに向いている人」の条件とも言える。逆に言えばこれにまるで当てはまらない人は「仕事に向いてない」ということにもなるかもしれないが、正直世の中、これらをすべて身につけている人のほうが珍しいし、そうでなければまるで仕事にならないというわけでもない。
だから、万が一だれかに、「自分はこれらに当てはまると自信を持って言えなければ、翻訳家を目指すべきではない」などと言われても、そんな者に自分のオールを任せなくていいと、わたしは思う。
では、これらの条件のうち、最後のひとつはどうだろうか。
「センス」は存在するかもしれないけれど
翻訳というものが文章を書く作業である以上、「よい文章を書く力」はやはりある程度はないと困るだろう。文章を書くセンスがある人というのは確かに存在する。たとえば運動でも、あまり走る練習をしなくても最初から足の速い人がいるように、たいした量を書いていなくても、最初から文章がうまい人はいるものだ。
「日本語でよい文章を書く力がある人」というのはしかし、「最初からよい文章を書くセンスがある人」とイコールではない。
以前、某所で翻訳を教える講義をもたせて頂いたとき、教室に50代くらいの男の人がいた。その人が書いてくる文章は当初、いかにも直訳といった感じでぎこちなかったのだが、数カ月がたったころ、あるときを境に、ふいにガラリと印象の違うこなれたものになった。以前と同じ人が書いたものとは思えないような大きな変化に、ひどく驚かされたのを覚えている。正直、そのまま勉強を続ければ、仕事にもできるのではないかと思ったほどだ。
その人が具体的にどんな学習をし、そこでどんな発想の転換があったのかはわからない。けれど、この経験以降、わたしはセンスというものをあまり信じなくなった。
この人が最初に書いてきた文章にはなかった「センス」が、同じ人が数カ月後に書いた文章には確実に存在した。これは、この人にはそもそも「センスがあった」という風にも言えるが、一方で、「センスがあるかないかなど、だれにもわからない」とも言える。
だれかに「センスがあるかどうか」なんて、結局自分にも、他人にもわからないのだ。「今そこにあるセンス」がだだ漏れになって見えている人もいれば、これから育つ人もいる。だから、翻訳の学習をする人は皆、今の実力とは関係なく、「自分にはセンスがあるかもしれない」と思っているのが吉だ。
「嫌いなものがそんなにない」
とはいえ、「『自分にはセンスがあるかもしれない』と思っているのが吉」などというのは、やはり翻訳以外の仕事にも言えることかもしれない。では翻訳という仕事に特有の、あった方がいい適性とはなんだろうか。
わたし自身が翻訳の仕事をするうえで、何がいちばん役に立ったかと考えてみたところ、出た結論は「嫌いなものがそんなにない」だ。
出版翻訳にせよ、産業翻訳にせよ、映像翻訳にせよ、だれか他人からの「これを訳してほしい」という需要があってはじめて翻訳という仕事が生まれる。だからこの仕事においては、常に自分の好きなものが訳せるわけではない。というより、十中八九、自分が好きなものは訳せない。
まだ翻訳の仕事を始めていない人や、始めて間もない人は「翻訳の仕事ができるならどんな内容でもいい」と思うかもしれない。しかし実際に嫌いなものやまったく興味のないものを、ひとりで延々と、場合によっては何カ月も訳し続けるというのは、わりとつらい作業だ。
これを解決する方法はふたつあって、ひとつは「自分が○上春樹くらいの大物になって訳す対象を選べるようになる」、もうひとつは「嫌いなものを減らす」であり、言うまでもなくおすすめは後者だ。
「好きなものがたくさんある」でも悪くはないが、これは「嫌いなものがそんなにない」とはちょっと違う。翻訳を仕事にしたいという人にはおそらく、本が好き、映画が好きという人が少なくないだろう。だからこそ「好きなもの」をよく知っているし、こだわりもある。それが翻訳をするうえで大きな強みとなる面はたしかにある。けれどやはり、翻訳という仕事において自分の好きなものだけを訳せる人は、実際にはほとんどいないのだ。
一方で「嫌いなものがそんなにない」のであれば、「○○を訳してほしい」と言われたときにそれを喜んで引き受けられるチャンスが増えるし、喜んでやる仕事はよい訳文という結果につながる。
嫌いなものを無理に好きになる必要はないし、実際にそうそう何でも好きになれるものではない。けれど、単に知らないという理由で拒否感を抱いているものについて、ある程度触れることで馴染みを作っておくというのは、そこまで難しいことではないだろう。
だからたとえば、普段は小説ばかり読んでいるという人は、たまには手にとったことのないビジネス本や占い本を読んでみるのもいいかもしれない。
世の中にどんな需要があって、どんな仕事が来るかは、そのときになってみなければわからない。嫌いなもの、知らないものを減らしておけば、仕事を喜んで引き受け、よい仕事ができることにつながる。だれにも(たぶん神様にも)わからないセンスのあるなしよりも、嫌いなものの多い少ないを考えてみることをおすすめしたい。

北村京子
ロンドン留学後、会社員を経て翻訳者に。訳書にP・ファージング『犬たちを救え!』、A・ナゴルスキ『ヒトラーランド』、D・ストラティガコス『ヒトラーの家』、M・ブルサード『AIには何ができないか』、J・E・ユージンスキ『陰謀論入門』(以上、作品社)、『ビジュアル科学大事典 新装版』( 日経ナショナル ジオグラフィック社、共訳)など。