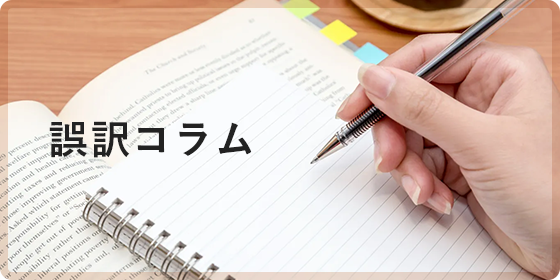海外だより
2024.06.13

我が家の家庭菜園
巷では、ドナルド・トランプ元大統領が、2020年の大統領選挙戦に際して「不倫口止め料」を支払い虚偽記載したことに対し、有罪が確定したことが話題になっている。陪審員全員(12名)が「34件の罪状全てに有罪評決」で合意したことは、私には驚きだった。トランプは、この判決に対し控訴する予定だそうだが、この判決で11月の大統領選挙の行方が不透明になってきた。
しかしアメリカでは、有罪判決を受けたとしても選挙に出馬できるし、勝利すれば大統領もなれるらしい。ひぇ〜、もしトランプが大統領になったら、子供達に「この国の大統領は、有罪判決を受けて犯罪者になった人だよ。悪いことしても大統領にもなれる国って、すごいね」と言うのかな?
そのような最中、我が家では、5月恒例の野菜畑作りをした。毎年この時期には夫の大学の日本伝統芸能の学生公演があり、私自身も衣装の準備で忙しく、畑作りはどうでもいいやと思うこともあるのだが、庭から取れる野菜の美味しさは諦めきれない。
1987年に最初の家を買った数年後から野菜畑を始めたので、家庭菜園歴は30年以上になる。
なぜアメリカで野菜畑を作り始めたか
夫と結婚してアメリカで暮らすようになって、一番がっかりしたのはキュウリが美味しくなかったことだった。当時は、表面にワックスを塗ってあるものしか食料品店には売ってなかった。キュウリの皮はワックスでベタベタしていた。
 アメリカの典型的なワックスを塗ったキュウリ(下段)。
アメリカの典型的なワックスを塗ったキュウリ(下段)。
現在は 日本のキュウリと味が似たオーガニックのEnglish Cucumber(中段)や
Persian Cucumber(上段袋入り)も1年中売られていて結構美味しい
私の母は、私を妊娠していたとき毎日キュウリを山のように食べていたと聞いた。7月生まれの私は、きっと母の母乳もキュウリの味がしたに違いない!
そんな私の一番好きな野菜はキュウリであった。夫と結婚しアメリカに移ったために美味しいキュウリが食べられなくなってしまったのは、本当に悲しかった。
それでも食べるのを諦めきれない。ワックス塗りの皮を全部剥いて中の種を取り出してどうにか食べた。後でわかったのだが、キュウリは比較的腐りやすく、冷蔵庫に入れておくと次第に皮が腐りヌルヌルし始める。それの防ぐための対策がワックスに違いない。
数年間は我慢していたが、家には狭いが庭もあったので、夏の間だけでもいい、日本で売っているようなキュウリが食べたいと庭の片隅に数本のキュウリとトマトの苗を植えることにした。苗といっても種類もたくさんあるのでわからない。とにかく日本のような「細くて長い胡瓜の写真のラベル」がある苗を買って植えてみた。
南に面した庭に植えた数本のキュウリとトマトの苗は、私たちの期待を裏切らず見事においしい実をたくさんつけてくれた。私は、夏の間だけでもおいしいキュウリを食べられれば、残りの9ヶ月間我慢できると思った。この家には6年間住んだが、毎年夏の間は思う存分食べて満足した。
新しい家を探す
子供たちの学校教育のために息子が小学校に上がる前に引っ越しを決めた。家を探すにあたって庭に関しては、裏庭が南向きであること、子供たちが自宅の庭で安全に遊べること、そして、小さな野菜畑を作れることを望んでいた。
1年ほどかけて家探しをした。学校区の教育環境が良いことが最も大切なことであったが、私には、やはり野菜が作れる庭があることは悲願であった。
幸い、裏庭が南向きで比較的条件に合う家を探すことができた。
畑に向かない粘土質の土
新築であったため、庭作りはされておらず、夫と私は自分たちの好きなように庭作りができた。もちろん畑も陽が当たる庭の片隅に作ることにした。
ところが、この地方は11月から雨季に入り、翌年5月くらいまでシトシトと冷たい雨が降る。南向きと言っても地面は固く粘土質で野菜畑には全く向いていない。9月に引っ越し、土を掘り起こし、冬場に育つ大根を植えてみた。大根は、直径2センチ長さが10センチにしか育たなかった。冬場の野菜作りは諦めた。
コンポースト堆肥作り
私は、まず堆肥を作って、野菜の肥料にしようと思った。大きなコンポースト用のコンテナを買ってきて庭の隅に置いた。料理で生じる全ての生ゴミをここに入れる。タンパク質食品、つまり肉などは入れない方が良いという意見もあるが、私はとにかく「土に還る」ことができる食べ物は全てこのコンテナの中に入れた。
1年をかけて作った堆肥を5月に全て畑に入れ、大袋の「砂」と「ピートモス」を買ってきて混ぜ庭の土作りをする。夫も次第に熱を入れるようになり、小さな耕運機を買って土を耕し始めた。
 耕運機を使って土を耕す夫。毎年5月、我が家の行事だ
耕運機を使って土を耕す夫。毎年5月、我が家の行事だ
11月の雨季のシーズンになると、庭に落ち葉が半端なく落ちてくる。庭に植えた木が大きくなるにつれ落ち葉の量は増えていった。それら全てを冬の間この畑において置く。落ち葉の掃除は大変だが、野菜畑の堆肥になると思えば悪いものではない。落ち葉を冬の間畑においておくことは、雨の多いこの地域では土が固く粘土質に戻るのを防ぐ。またこの落ち葉で畑には草が生えない。耕運機で耕して混ぜ込む落ち葉は自然の堆肥であり、一石三鳥である。
 11月に集める庭の落ち葉と庭の隅に置いたコンポーストの入れ物
11月に集める庭の落ち葉と庭の隅に置いたコンポーストの入れ物
奥右側の囲いは蕗と茗荷の家だ。春先には「蕗のとう」が食べられる。茗荷は100個以上取れるので、生、天ぷら、酢漬けなどして楽しむことができる。日本人の友人にあげるととても喜ばれる。
 左が蕗、右は茗荷。果てしなく増えるので囲いに入れている
左が蕗、右は茗荷。果てしなく増えるので囲いに入れている
野菜畑を広める
毎年、植える野菜を増やしていった。その為畑の面積も少しずつ大きくなっていった。しかし、アメリカの家といっても、集合住宅地の中の家である。大きさも日光が当たる場所や時間も限られている。
それでも10年を過ぎたくらいから、土は驚くほど肥え、どんなものを植えても夫婦と子供2人が食べるには十分の夏野菜が取れるようになった。
20年近く経つと土は真っ黒になり、手で掘り起こせるぐらい柔い土壌が出来上がった。今は夫と2人分の野菜には多すぎるため、義母や友人たちに食べてもらっている。毎年畑の準備は大変ではあるが、もぎたての野菜の美味しさと収穫の喜びは格別である。友人たちもおいしい夏野菜をもらって感謝してくれる。


7月中旬から10月半ばまで毎日食べきれないほどの野菜が収穫できる
怪物現る!!
そのようにして何の問題もなく25年近く夏の家庭菜園を楽しんできた。
ところが、である。この庭に突如「小さな怪物」が出没するようになった。
ポートランド近郊は、近年他州から引っ越してくる人が急激に増え、住宅供給不足が問題となっている。そのため、この近くの森や林、緑地地帯、牧場や畑がデベロッパーによって開発され、何百何千という家が建ち始めた。
我が家から車で30分ほど西に行った地域では、数年前から開発が進み、家やアパートを含む8000戸の住宅が建てられ、20,000人以上が住むことになる。そこには学校、スーパーから病院まで建設されている、一つの街が作られる。
このような多くの開発事業で、近隣の森や林で静かに暮らしていた鹿、コヨーテ、ウサギ、リス(リスは、この地方にはどこにでもいて、我が家の庭やフェンスの上を毎日元気よく走り回っている)など行き場を失って住宅街に食料を求めるようになった。住民にとって怖いのはコヨーテで、飼い猫や小型犬を外に出すことは危険極まりない。裏庭が広い野原に面している家をもつ友人は、庭にコヨーテがこないように光センサーをつけビデオカメラも設置した。ある日のカメラには、コヨーテがウサギをパクリと一飲みで食べてしまっている様子が映っていたと驚いていた。
2020年5月下旬、いつものように野菜の苗を植え、野菜たちは順調に育っていた。
7月に入り(この地方は、緯度が札幌と同じぐらいなので、5月末ぐらいまで肌寒く7月中旬から野菜が採れ始める)、畑に行って見ると「おかしい、変だ!!」茄子と枝豆の苗の上の部分がなくなっている。食いちぎられたようだ。
「誰?なに?こんなことするの!」この家に25年近く住んでいて初めてのことだったので、何が起きたのか見当がつかない。寒さで苗が枯れてしまうことがあっても育った苗のてっぺんが突如なくなることはなかったからだ。

 ナイフで切ったかのように食いちぎる
ナイフで切ったかのように食いちぎる
夫と私は、庭をじっと観察することにした。
見つけた!怪物は「ウサギ」であった!
ウサギは、枝豆と日本の茄子だけ食いちぎって、キュウリ、トマトやピーマンには見向きもしなかった。和食好みのウサギのようだ!しかし、いくら可愛いと言っても、毎朝枝を食いちぎられた苗を見るのは耐えられなかった。
 庭に初めて現れたウサギ!
庭に初めて現れたウサギ!
畑を守る対策は?
色々と考え、フェンスで囲むことにした。厚手のプラスティックのフェンスを夫が買ってきた。そして畑全体を囲んだ。
ところが、である!
ウサギも負けてはいない。とても美味しいのだろう、これを諦めるわけにはいかない!全身全霊で立ち向かおう!と思ったかどうか?
このプラスティックのフェンスは、見事に15センチ四方の穴を綺麗に食いちぎって開け、美味しい枝豆と茄子をお食べになっていたのだった。
 自分の体が入る大きさだけ四角く穴を開け入っていく
自分の体が入る大きさだけ四角く穴を開け入っていく
プラスティックフェンスの強度は結構強く、ウサギの歯と顎の強さには驚いた
唖然とした夫と私は、翌日、どうしたら良いかと考え、罠を店から買ってきて仕掛けた。人参と美味しいレタスを入れた・・・。しかし、うさぎは人参にもレタスにも見向きもせず、またフェンスを食いちぎって中に入ってしまった。はて?ウサギは人参が好物ではなかったか?
 店から買ってきた罠。結構大きいので値段も高かった
店から買ってきた罠。結構大きいので値段も高かった
人参を手前に置いて誘導してみたが・・・
私の怒りは頂点に達し、「このままでは美味しい茄子も枝豆も全滅だ!」と、プラスティックのフェンスを取り払い、今度は鶏小屋用の金網のフェンスを買ってきた。ウサギが穴を掘って中に入らないように20センチほど土に埋めて畑を囲った。
ここまでで数百ドルかかった。野菜は買った方がず〜〜っと安かった・・・。
夫と私の畑にかける労力とお金は半端ない!
フェンスに扉をつけ野菜を収穫するのは不便であったが、どうにか夏を乗り切った。
 金網のフェンスで畑を取り囲んだ
金網のフェンスで畑を取り囲んだ
その後のウサギ対策
2021年、夫と私は、初めから金網フェンスをつけた。ウサギは春先に庭で見かけるようになり、我が家の野菜を待っているように見えた。これからず〜っとフェンスの中で野菜を育てることになるのだろうかと思うと憂鬱だった。
私は、日本人学校補習校の中学生を長い間教えていた。パンデミック中のZOOM での授業中、野菜畑のウサギとの格闘を生徒たちに面白おかしく話した。
すると一人の男子生徒が「うちの親は、韓国唐辛子の粉を野菜の周りに蒔いてウサギ対策をしているよ」と教えてくれた。
「わ〜〜い!!フェンスをつけなくてもいい!」と大喜びで韓国食料品店に行き、たくさん唐辛子の粉を買ってきて蒔いた。ウサギは近寄らなくなった!大成功!
唐辛子代は高くかかったがフェンスを張らなくて良いことは、本当に気分がよかった。
今年の秘策
2023年までこの唐辛子対策は、どうにか少し効果があった。しかし、この頃になるとウサギも唐辛子に慣れてきたのか、雨上がりの後や私たちが忙しく数日何もしないと唐辛子効果が薄まる。そこを狙って上手に枝豆と茄子の苗を食べるようになった。我が家の唐辛子代金は、ばかばかしいほど高くかかるようになった。
私は、どうしたらいいのか悩みに悩んだ・・・。
義母は、メリーランド州に住んでいた時、ウサギが庭に来ると昔アーチェリーを習っていたので、弓矢でウサギを狙い撃ちしたそうだ。
脅すには、アメリカでは鉄砲か?我が家には鉄砲はないし・・・。
 粉唐辛子作戦も効かなくなって見事に食いちぎられた枝豆
粉唐辛子作戦も効かなくなって見事に食いちぎられた枝豆
これで決まり!!
私は唐辛子効果をまだ完全には諦めていなかった。粉ではなく唐辛子そのものをまわりに置くのはどうだろうか。しかし、広範囲に捲くとなると値段が掛かりすぎる。
考えに考えた・・・。
「そうだ!周りにおいてもダメなら、苗そのものに唐辛子をつけるのはどうだろう?いくらウサギでも、食べた苗がピリピリ、ヒリヒリとしたら耐えられないだろう。食べたら目が飛び出るかもしれない。自然界を生き抜く野生の動物たちは、生きるための知恵を十分に備えている。嗅覚も人間よりはるかに優れている。このような苗には近づかないだろう」と、私は予想した。
私は、早速唐辛子を買ってきて鍋に30本ぐらいいれてグツグツ煮た。エキスを抽出し、その液を濾してスプレー容器に入れ、苗そのものにスプレーする。私の最終案だ!
苗を植えたその日から毎日苗に唐辛子を直接吹きかけた。台所で唐辛子を煮るだけでも私自身目が痛くなり咳やくしゃみが出るほどなので、嗅覚が発達した動物なら遠くからでも匂いを嗅ぎ取れると思った。
 唐辛子を切って種を出し煮詰める。濾してスプレーボトルに入れる
唐辛子を切って種を出し煮詰める。濾してスプレーボトルに入れる
私は念には念を入れスプレーで唐辛子エキスを吹き付けた後、茎と葉の付け根に煮込んだ唐辛子を置いておいた。戦いが始まった!
夫は不安そうに、「そんなに毎日唐辛子を苗にかけていたら、枝豆やナスは唐辛子の味がするのではないか」と私に聞いた。
私は、「苗が大きくなって実をつける頃には、もう唐辛子の役目は終わっているから大丈夫!」自信を持って答えた。


唐辛子エキスを吹きかけた後、煮込んだ唐辛子を枝に挟んだ
「大成功!!勝ったぞ〜!」ウサギはこの唐辛子スプレーをかけるようになってから、庭には来なくなった。
我が家の野菜畑は、今年もたくさんの野菜を実らせて食卓を彩ってくれることだろう。ウサギが来なくなってちょっと寂しい?

田中 寿美
熊本県出身。大学卒業後日本で働いていたが、1987年アメリカ人の日本文学者・日本伝統芸能研究者と結婚し、生活の拠点をオレゴン州ポートランドに移す。夫の大学での学生狂言や歌舞伎公演に伴い、舞台衣裳を担当するようになる。現在までに1500名以上の学生たちに着物を着せてきた。2004年から教えていた日本人学校補習校を2021年春退職。趣味は主催しているコーラスの仲間と歌うこと。1男1女の母。