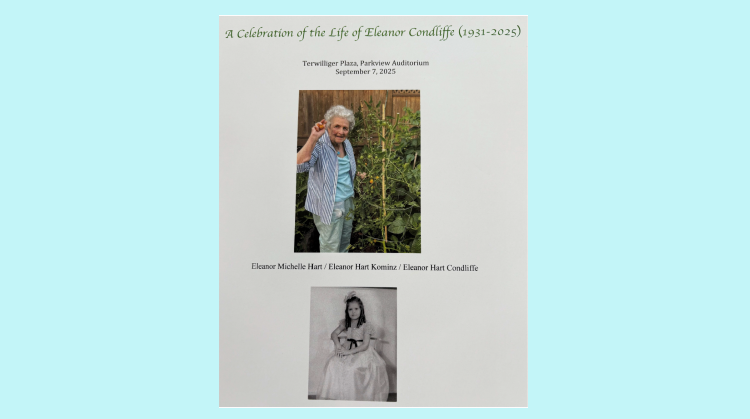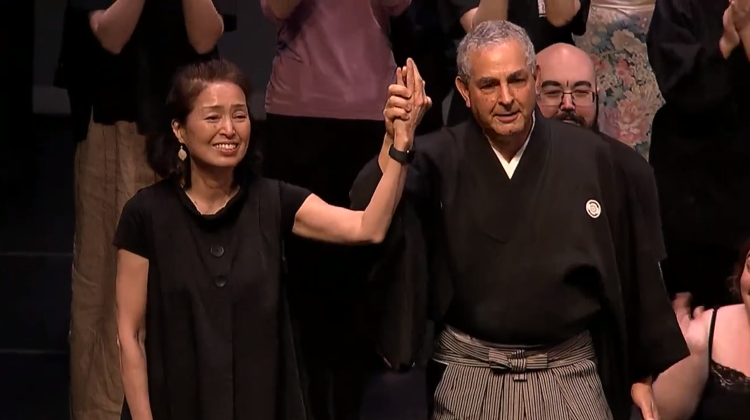海外だより
2024.02.01

季節の挨拶
幼い頃父の仕事の関係で名古屋に引っ越した。3年半ほどを“見知らぬ”“言葉も違う”土地で過ごしたわけだが、この時間が私のその後の人生に大きな影響を与えたことは今になるととてもよく分かる。
転勤族という“人種”であることの自覚のようなものが芽生えたのが名古屋だった。言葉――単に方言にすぎないのだが――が通じないことに7歳は少し慌て、そしてめいっぱい想像力を働かせることを覚えた。「自分はずっとここにいるわけではない」ということも官舎住まいの生活を通して理解した。そしてそれは、少し大きくなってから「手紙を出す」という習慣につながった。今では死語にもなったかもしれない「文通」である。きれいな便箋や封筒、そして切手にも興味を持った。
 名古屋城にしゃちほこがいない!
名古屋城にしゃちほこがいない!

と思ったら地上に降りて来てくださり、、、
2021年4月のことでした(16年ぶりの特別展覧)
 私が通ったのは、お城の近くの「東白壁小学校」
私が通ったのは、お城の近くの「東白壁小学校」
しゃちほこが校章にデザインされています。
小学校5年生の時に東京に戻ったのだが、東京っ子であった母が嬉々として帰る――その当時は、今と違って頻繁に里帰りなどできない時代だった。新幹線のできる前の東海道線では、5時間以上の距離である――のを横目に見ながら、私は仲良しと別れることがやはり寂しかった。だから、当然のように住所を交換し、東京に帰ると親友M子との文通が始まった。
 家の天袋にぎっしりと手紙の段ボール箱。
家の天袋にぎっしりと手紙の段ボール箱。
文通は、最初はそれなりに頻繁だっただろう。でも、ほどなくすると新しい生活にも慣れて、そちらのほうが楽しく、忙しく、手紙を書く頻度は急速に少なくなったに違いない。年賀状だけのやり取りになってしまったかもしれない。
ただ、お互い大学生になった頃にM子は東京に遊びにやって来て、7-8年ぶりに再会したのだから、「文通」はそれなりに続いていたということでもある。地元の女子大に進んだ彼女が嬉しそうに“東京の街”――当時私が住んでいた官舎は赤坂の乃木坂にあり、六本木も徒歩圏――を歩くのを、なんだか不思議な気持ちで見つめていたことを今でも覚えている。
 乃木坂に住んでいた高校生の私。桧町公園にて。
乃木坂に住んでいた高校生の私。桧町公園にて。
現在はもっともっときれいに整備されて、ミッドタウンの大きな庭に。
幼馴染のM子だけではなく、女の子ばかりの私立中学に進んだ私に手紙をくれた小学生時代の同級生の男の子とのやり取りも2-3年は続いたし、「ペンパル」としてアメリカの同年代の女の子とも文通した。辞書を引き引き、拙い文章を綴り、海の向こうから届く筆記体の美しさに見とれた。
こんなふうに「書くこと」が人と人を繋ぐ重要なツールであった時代、現代の若者たちにしたら“想像を絶する”七面倒臭さかもしれないが、私にとっては“古き良き時代”でもある。
手紙を認める、、、という機会の本当に少なくなってしまった現代日本社会にあっても、年賀状だけはかろうじて残っているようで嬉しい。
一年に一度しか文通しないとしても、一つの節目としての挨拶はそれなりの意味を持つ。それは、何も日本民族だけに限ったことではない。海外駐在時には仕事関係も含めて、たくさんのグリーティングカードをそれこそ世界中に送っていたのだ。
欧米では「封書入りカード」が一般的で、貰った美しいカードは、必ず居間のデコレーションとなっていたのも楽しく思い出す。だからこそ、せっかくの良い風習は世界中に残ってほしいと思う。できれば、きちんと紙の上に残すような形が望ましい。そんな気持ちで、いつも欧州にも何通かの賀状を送ったりもする。
日本の年賀状は、「なるべく元旦に届けたい」という考えがあるから、年末の忙しい時期に必死に書いたりもするのだが、そんな時は、海外の習慣が羨ましくもある。彼ら(私が知る範囲のいろんな国、いろんな宗教の人々)は“季節の挨拶”をてんでばらばらに送ってくるのである。
12月の声を聞けば、そういったカードが届き始める。「メリークリスマス」もないわけではないが、様々な宗教に配慮して、「良い休暇を」「良いお年を」「新年おめでとう」というカードが多い。誰もが祝えるのが“新しい年が来ること”なのだ。それは年をまたいで、1月末まで続く。
日本ではすっかり正月気分も抜けているころに、「今年もよろしく~!」と“賀状”を送る人々の何と大らかなこと!!
もっとも、太陰暦を残すいくつかの国は年によっては2月に入ってからの新年もあるから、何の不思議もないのかもしれないけれど。
昨今では、“メール添付”というような形も増えてきて、だからこそ、実際のカードや書状が各国の郵便局を通して送られてくれば猶更嬉しくもある。
 去年フランスから届いたカード。
去年フランスから届いたカード。
エリザベス女王ご逝去の後、フランスでは切手が発行された。
賀状来る逝きし女王の切手もて ちづこ
年賀状は郵政省に“乗せられて”、特に戦後始まった「お年玉年賀はがき」に惹かれて急速に広まった、というのもあながち嘘ではなさそうだが、それはそれで楽しい習慣だと思う。私も物心ついた頃から、我が家に届く――それはもちろんほとんどが父宛ではあったけれど――年賀状の当選番号を調べる役目を楽しみにこなしていた。年末の「紅白歌合戦」と同じように、一月の恒例の行事だったのだ。
長く海外に暮らしたから、「お年玉はがき」を期待できないことも何年もあったが、2017年に帰国してからはまた復活させて今年も“めでたく”切手を何枚か頂戴した!
最近は、財政事情もあるのか、「お年玉」の当たる確率がぐっと減ってしまってはいるけれど・・・別にお年玉を当てにしているわけではないけれど・・・
きちんきちんと当選数字を調べながら再びそれらの賀状に目を通し、手書きのものなどはさらにゆっくりもう一度読んだりする。
 お年玉年賀はがきの当選切手。昭和47年(1966)からのを取ってあり、今でも使う。
お年玉年賀はがきの当選切手。昭和47年(1966)からのを取ってあり、今でも使う。
 今年のデザインは、源氏物語の影響? 珍しく干支との関連が分からない。
今年のデザインは、源氏物語の影響? 珍しく干支との関連が分からない。
新しい年を寿ぎ、誰彼のことを思いながらふみを書くこと、読むことの幸せ。この一年に一度の挨拶を、世界中の人々が心を込めて送り合える時はいつになったら訪れるのだろうか。

北原 千津子
東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。