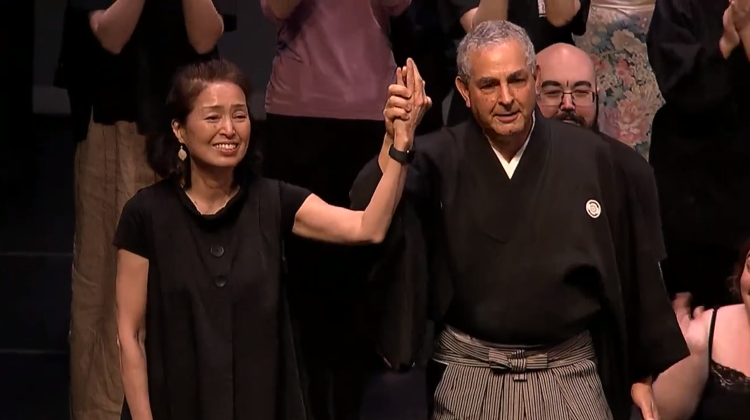海外だより
2022.05.20

外国で暮らすということ(2)
学生時代に度々欧州に出かけていたが、実際に住んでみて改めて感じたことがたくさんある。その一つに、日本という環境と欧州という環境の「根本的な違い」を肌で感じたということが挙げられる。
良くも悪くも、日本は「島国」である。
夫の転勤に伴って最初にパリに引っ越したのは1978年のことだった。私は大好きなパリに住めるというだけで大満足で、しかもまだ子供はいないし、大学の授業を聴講したり、画廊でアルバイトをしたり、せっせとフランス文化を吸収することに努め、かつフランス式生活(ヴァカンス!)を大いに楽しんだ。その頃日本ではようやく週休2日が導入されたばかりだったと思うし、「長期休暇」など夢の夢。せいぜいお盆やお正月の4-5日間という時代。まして海外旅行に誰もが気軽に出かける時代ではなかった。

 毎夏訪れた南仏サントロペの港と浜辺。
毎夏訪れた南仏サントロペの港と浜辺。
カフェの椅子重ねしまひてパリ文月 ちづこ
いたって能天気に暮らしていた私ではあるが、16区のアパルトマンに住みフランス生活を謳歌する中で少しずつ見えてきたことがある。それは欧州大陸の中のフランスという国の“意味”でもあった。
コンシエルジュ、今では日本でもちょっとカッコつけて、何かの窓口のような所、そこで専門的に対応してくれる職種の名称に使っているようだが、もともとはフランス語の“門番”“集合住宅の管理人”という意味である。そして、それは職業としては決して高い地位、つまり高給のものではなく、むしろ底辺層に属し、最低賃金の指標となるようなものでもある(*)。
私たちが住んだ建物のコンシエルジュはマダム・ペトロビックという色白の金髪の美しい中年女性で、割とインテリ風のご主人(毎日ノーネクタイで通勤していた)と、建物地上階の小さなステュディオでつましい暮らしをしていた。
用事があってステュディオのガラスの扉を叩くと、内側にかけられたレースのカーテンが少しだけ開いて、そこから口をきゅっと結んだ彼女の、おずおずと警戒するような目が一瞬覗く。でも次の瞬間にはにこっと笑って、扉を大きく開けてくれるのが常だった。
当時の商社マンの海外駐在はそれなりに忙しく、夫は毎晩のように「接待」。大きな会議とか海外企業とのおつきあいなど、日本から夫人を伴っておみえになる方も時々あって、そんなときには私も接待要員となった。
街を案内したり、買い物の通訳をしたり、超高級フランスレストランでのお相伴などなど、それはそれは楽しいことがたくさんではあったが、忙しいことに変わりはない。そんな私の日常生活を助けてくれたのがマダム・ペトロビックだ。
 パリ16区。住んでいた建物の入口扉。
パリ16区。住んでいた建物の入口扉。
建物の6階最上階には大家さん家族が住んでいたが、マダム・ペトロビックは大家さんのアパルトマンのお掃除も引き受けていて、4階の我が家もやってくれると言う。本当に助かった。
私が使っていたのは、とても大きな重たい掃除機で、これは犬養道子さんが78年にパリから引越される時に譲ってくださった日本製(業務用だったのかもしれない!?)の優れものだったが、マダム・ペトロビックは、その強い吸引力を盛んに「素晴らしい」と褒めてくれた。
79年、80年と続けて出産してからは、子供たちのこともとても可愛がってくれて、彼女が掃除をしている間、ついでに赤ん坊のことも見てもらいながら私は近所の買い物に走ることもできた。
掃除の時に、彼女が写真立を落としてしまい、カバーのガラスが割れてしまったことがあった。
「物は壊れることがある」と常々思っている私は、必死に謝る彼女に「ガラスですもの、気にしないで」と言った。でもまじめな彼女はどうにか弁償したい、と言う。
そして、数日後、「夫が作ってくれたの」と、硬いプラスティックをはめた写真立を大事そうに胸に抱えて持って来て、前と同じ棚に置いた。
それは、生まれたばかりの子供と私の写った2枚組の写真立だった。
 2枚組の写真立
2枚組の写真立
どんどん親しくなっていったある日、私は思い切って彼女の出自を尋ねた。
コンシエルジュという職業、名前、容姿、そして訛りのあるフランス語を聞いていれば、彼女が決して平凡ではない生活を送ってきたのだということは想像がついていたから、何となく聞くのを躊躇っていたのだ。
「国はね、ユーゴスラビア。でも捨てたのよ。もうあそこでは生きていかれない」
「国を捨てる」という言葉は、私には簡単ではなかった。パリにはそれこそ移民がたくさん住んでいたし、ソ連から亡命してきたバレリーナの舞台も観ていたから、「いろいろなこと」を頭では理解できる。でも、どうしても分からない。その後90年代になって、ユーゴは分裂し、各地で内戦が起こることになるなど、当時はもちろん知る由もない。
ただ、身近に彼らがいる、ということは紛れもない事実として私の肌に染みこんだ。「国とは何か」「民族とは何か」ということを考えるようになった。
1984年、駐在を終えて日本に帰る私に、マダム・ペトロビックが「一つだけお願いがある」と言った。
「あなた方の写真、おチビちゃんたちの写真を一枚だけくださいな。」
もちろんですとも、と私は少し大きく引き伸ばした私たち家族の写真を置いてきたが、彼らの写真が欲しいとは頼めなかった。彼らのステュディオには、だいぶ若い時と思われる彼女の写真が一枚飾られているだけだった。

北原 千津子
東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。