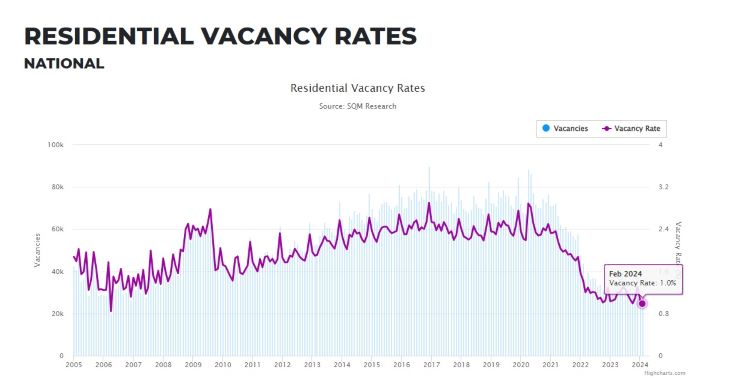海外だより
2022.02.24

2020(その2)
日本に本帰国して二年余。日本に落ち着いたとは言いながら、それでも年に2回くらいは欧州など「海外」に出かけていた夫と私だが、2020年は久々に日本を一歩も出ない年になる。夫に至っては、「久々」どころか、大学生になって以来半世紀ぶり、という特異な年となった。
1月末に、上海に住む息子が中国でのコロナを避けるべく家族を帰国させた。「子供はあまり感染しない」という情報は当初少なかったから、何となく「おちび達は日本のほうがいい」という判断だったのだ。
武漢からはるか遠い上海ではあったが、「今まで経験のない事態が起こっている」という不気味悪さを私たちは感じていた。
ただ、実のところ、2020年1月の時点で、日本全体には「恐怖心」は広がっていない。たまたま、私たちにはパリやロンドンに多くの友人知己があり、また、いまだに情報を発信し続ける(私のメールアドレスに入ってくる)市役所からのメールなどで、欧州の尋常ならない雰囲気を察したからにすぎない。
前の年の暮れに突如発生した「新型コロナ」というウィルスがいつの間にか欧州に飛び火し、あれよあれよという間に広がっていく状況に社会全体が怯えていた。
連日、欧州のニュースにはCOVID-19という名詞が飛び交っている。その感染力は今までの常識をはるかに超えるものだったから、誰もがどうすれば良いのか判断する間も無かったのかもしれない。結果、多くの国が「禁足令」を発せざるを得ない状況へと陥っていた。
そんな欧州からのニュースや、知人たちからのメールのいくつかは、東京にいる私たちをも震えさせた。古巣のパリやロンドンがまさに喘いでいるのだ。人っ子一人いないパリのシャンゼリゼの映像はただむなしく、寒空の下スーパーマーケットに2メートルもの間隔をもって並ぶ人々の列も侘しさが際立っていた。
そのうち日本もこんなふうになるのだろうか、、、日本だけが免れることはまず不可能ではないだろうか。
としたら、できることは、なんだろう? それまで度々あった様々な会食をやめ、繁華街に出るのも控えよう、などと漠然と考えていた2月。3月に入ると東京にも少し「緊張感」が生まれ、母がお世話になっていた高齢者施設では面会に制限を設けるようになった。
お正月は我が家でお節料理に舌鼓を打っていた母が、体調を崩したのはそんな頃だった。
ちょっと転んだとかで骨折したわけでもなかったのだが、「歩きたくない」「食べたくない」と言い始めたかと思ったら、96歳は途端に「病人」になってしまった。そして2週間ばかり寝込み、生涯を閉じる。6年前の4月に同じく96歳の人生を全うした父の元へと旅立ったのである。
2020年は例年になく暖かい年で、庭の山桜がすでに散り始めていた。

東京都に初の「緊急事態宣言」が行われてからおよそ1週間。子供と孫とひ孫僅か十数名の野辺送りではあったが、祭壇は母の好きな淡いピンクの花々で溢れた。
その後、「宣言」はすぐに日本中に広がり、欧州に遅れること数か月、日本列島もご多分に漏れず、コロナ禍に喘ぐ、重苦しい雰囲気に包まれた。
政府はしきりと「新しい生活様式」を呼びかける。
好きな美術館通いができないだけではない。たまの外食も我慢。観劇も友人との集まりも句会もキャンセル。半径1キロくらいの土地から出ず、毎日三度の食事を夫と共にしながら、、、でも、ふと気づいたのだ。これは、2017年までのダカールでの生活とさほど変わりないのではないか!?
私にとっては「新しく」も何ともない、生活様式の中で、両親が旅立ってしまった実家の整理を再開した。
外出制限があり、人との接触を避けなければならない日々にあって、車を運転して1人で出かける実家は格好の私の「活動地」である。誰にも会わずに黙々と整理するのは、ある種の快感だ。1年前の空き巣騒ぎの後よりも熱がこもり、父方の祖父が整理していたアルバムを見つけた時には宝物を見つけたような喜びとなった。それは「コロナ」という言葉を忘れさせる貴重な時間でもあった。
一方、緊急一時帰国の息子家族。「滞在は3ヶ月もあれば十分、初夏にはまた上海に戻るだろう」と当初は思っていたが、そうは問屋が卸さない。日本の状況は海外への移動を難しくし、中国側もまた、受け入れ拒否となった。
そうこうするうちに滞在許可が切れるという事態にも陥り、私は一人上海に残る息子のことが気にはなったが、コロナ感染を食い止めている中国に少し安堵してもいた。
 ことわざかるたにオンラインバレエ教室等々、「コロナ」を乗り切る孫娘たち
ことわざかるたにオンラインバレエ教室等々、「コロナ」を乗り切る孫娘たち
オリンピックは延期となり、コロナと暑い夏とが相まって、何となく不自由なおちび達のために、大人も寝転んで水浴びができそうな、大きなビニールプールを買い、夫は、週末ごとにプール清掃員兼監視員の役を任ずる。何十年振りに手花火にも興じた。
結局息子の家族がまた一緒になれたのは、11月末。日本からの家族を受け入れる許可が出るとすぐに航空便を予約し、前日のPCR検査の陰性証明をもって、てんやわんやの上海行となったが、この顛末を書き始めたら何ページにもなってしまうので、また別の機会に。
私にとって(もしかしたら、世界中の人にとっても)決して忘れられない年となる2020年はこんな風に慌ただしく過ぎ去り、夫と二人だけの静かな元旦を迎えた。
楪や写真立またひとつ増え
俳句結社の新年号に寄せた句である。


北原 千津子
東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。